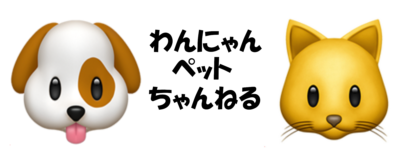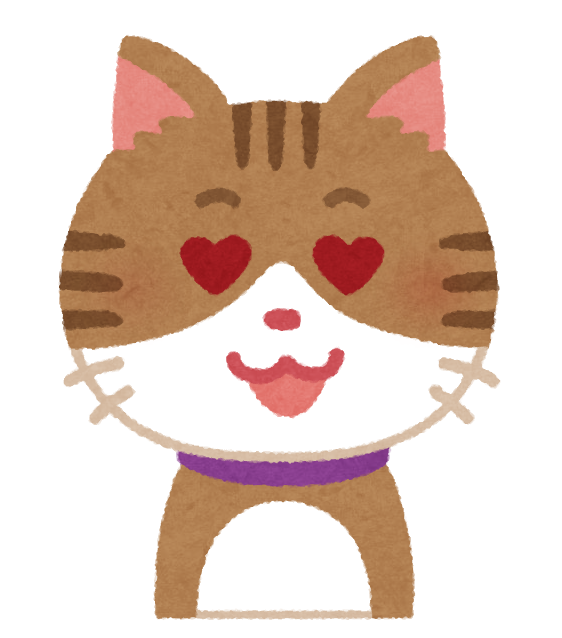犬のもっている力、についてです。視力、視野、色覚、聴覚、嗅覚などについてまとめてみました。
犬は人間にはない素晴らしい身体能力を持っています。
今回は、犬のからだや身体能力について、まとめてみました。
目(視覚)
視力
犬は人の視力で0.2〜0.3くらい。 近視だといわれています。
2〜3メートル以内のものしかハッキリと見ることができていないようです。
飼い主の顔も、10〜20メートル離れると、目では判断できなくなるようです。
しかし、動体視力はかなり発達しており、動くものであれば100メートル先でも反応することができます。
視覚では判断できない場合、嗅覚や聴覚などのほかの感覚で、様々なモノを識別します。
視野
視力が弱いかわりに、視野は2倍近くあります。
人間が約180度なのに対して、犬は約250度をみることができるといわれています。
また、暗がりでものを見分ける能力は、人間の8倍といわれています。
色の識別
色の識別能力が低く、見分けられる色は限られているようです。
青・紫・黄の三色は見分けることができ、青や緑、その混合色を見ているという説や、
赤色は認識できないという説も。
本当のところはまだ解明されていませんが、今後の研究によって解明されることを期待します。
第3のまぶた
マブタの内側には瞬膜という薄く白い膜があります。
マブタを閉じると同時に、左右の瞬膜が眼球を覆いしっかり保護しています。
鼻(嗅覚)
犬の能力で特に優れているのは嗅覚。
犬種や固体によって差はありますが、一般的に犬はニオイを嗅ぎ分ける能力が人間の約100万倍といわれています。
嗅覚
嗅覚細胞の数は、人が約500万個なのに対し、犬は約2億~数十億個といわれています。
この鋭い嗅覚をいかして、警察犬や麻薬探知犬、災害救助犬などが活躍しています。
一般的に目から鼻までの距離が長い犬ほど、嗅覚が優れているといわれています。
犬はニオイからの情報を元に、どう行動するべきかを判断してます。
相手の犬のお尻を嗅ぐ行為も、肛門腺のニオイから年齢や性別など様々な情報を集めるためとされています。
耳(聴覚)
犬の感覚の中で、嗅覚の次に優れているのが聴覚です。
音の大きさの聞き取りは人間の6倍、音を感じる範囲は人間の4倍、32方向まで聴き分けることができるといわれています。
聴覚が優れているため、突然の大きな音にはとても驚いてしまうので注意が必要です。
聴覚
寝ている間でも音をキャッチしています。
大抵の犬は警戒心が強く、普段聞きなれない変な音を聞きつけたら、たとえ眠っていたとしてもすぐに起きます。
聴こえる範囲
音を感じる範囲は人間の4倍
音を聞き取るだけでなく、どこらか聞こえてくるのかも正確に判別できます。
聴覚のよさと耳の形
犬の耳の形には「立ち耳」と「垂れ耳」があります。
一般的に「立ち耳」の犬の方が、音にはより敏感といわれています。
口(味覚)
犬は何でも食べる雑食タイプ。
味覚は鈍感で、味より匂いで食べ物を判断しているといわれています。
味覚
味を見分ける味蕾という細胞の数が、犬には人間の5分の1くらいしかないといわれています。
味覚は鈍感で、「旨味」・「苦味」などの繊細な感覚はなく、あまい/塩からい/すっぱいを感じることができます。
食べ物の好き嫌いは、匂い、歯ざわり・温かさの順で選んでおり、味はあまり気にならないようです。
人間と同じ雑食
犬は何でも食べる雑食タイプ。
祖先のオオカミは肉食ですが、人間と暮らすうちに徐々に変わってきたといわれています。
ただし、穀物や野菜を消化する能力が人間より低いので、過剰な摂取は禁物です。
歯
犬の歯も人と同じように、乳歯から永久歯へと生え替わります。
乳歯は28本、生後6週目頃に生えそろいます。
その後、5〜7カ月齢の頃までに永久歯が42本、生えそろいます。
犬歯が鋭く、臼歯も肉を引き裂けるように山型になっていますが、口の中に食べ物を入れた後はよくかまずに丸飲みします。
舌
犬は暑いときよく舌を出しています。
舌を出して呼吸を繰り返すことで、唾液を蒸発させて熱を体の外に放出しています。
胴(胸部/背中)
触覚
犬が触覚を感じるところは全身にあります。
耳のつけ根や背中、胸などをゆっくり撫でると、犬の気持ちが落ち着きます。
逆に、シッポやお尻周辺、鼻や口の周り、足の先などはとくに敏感で、犬にとっては触られるのが苦手な箇所です。
子犬の頃からたくさんスキンシップをとり、苦手な箇所も触れさせてくれるように慣れさせておくことが重要。
慣れさせることによって、成犬になってからの日常のケアや動物病院の診察などもスムーズに行うことができるようになります。
ヒゲ
犬のヒゲは本来「平衡感覚」や「センサー」としての働きがありました。
しかし、現代の飼い犬のヒゲは切ってもほとんど影響はないとされています。
被毛
被毛が上下の二重構造になっている犬種と、一重構造になっている犬種があります。
二重構造の犬は季節による生え替わりが発生するため、抜け替わる春先に毛がたくさん抜け落ちます。
一重構造の犬は季節による生え変わりは発生しません。
二重構造の被毛には、防水性の高い上毛(オーバーコート)と、保温性の高い下毛(アンダーコート)の2種類があります。
犬はもともと寒い地方原産の種類のため、被毛が生えかわるといわれています。
被毛には温度調整や皮膚の乾燥を防ぐ機能、細菌感染や外傷から皮膚を守ったりする役割もあります。
犬の毛は一定のサイクルで生え替わります。
屋外で過ごす時間が長い犬では、日照時間が長く暖かい春になると、冬毛が抜けて夏毛に衣替えします。
室内飼育の場合は、電灯という人工の光を浴びている時間が長く、気温の変化も少ないため、季節に関係なく1年中毛が生え替わる傾向があるといわれています。
オーバーコート
毛全体の外側を覆っているのがオーバーコート。
日差しから体を守り、体温が上がり過ぎないようにします。
防水機能もあります。
アンダーコート
内側にはやわらかく保温性の高いアンダーコートが生えています。
冬には、このアンダーコートが増毛し、寒さから身を守ります。
足
野生時代に獲物を追いつめる狩りをしていた犬の脚力は抜群!
速く走るだけでなく、長く走る能力にもすぐれています。
ジャンプ力もすぐれており、自分の体高の数倍の高さを飛ぶことが可能です。
しっぽ
シッポは、走ったり・飛んだり・泳いだり・急停止するための“バランス”をとる「かじ」の役目をします。
寒い季節では体を丸くし、シッポで鼻先を覆い冷たい空気を吸わないようにする、寒さ対策の役割も。
また、しっぽによって犬の気持ちを知ることができます。
- 元気にしっぽを振る・・・嬉しい、楽しい、大好き
- 唸りながらしっぽを振る・・・怒っている、威嚇
- 垂れ下がり足の間に挟み込むようにする・・・怖い、不安
コーギーやプードルなど、しっぽがない犬もいます。
そのほとんどは生まれつきではなく、断尾(子犬のうちにしっぽを切る)をしたからです。
まとめ
犬と人間は言葉を交わすことができません。
ですが、犬のからだについて知ることによって、少しでも犬との理解が深まっていくのではないでしょうか。
お互いによい関係を築き、楽しく暮らしていくことができればいいですね!
※人などとの比較(~倍)やその他の数値は諸説あり、多少の違いがあります。
おおよその目安としてください。
面白かったらぽちっとお願いしますU^ェ^U
にほんブログ村
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!